Jリーグ参入を目指す福山シティFC 監督・小谷野拓夢が考える、指導者ライセンス制度の在り方

社会人中国リーグの福山シティFCで監督を務める小谷野拓夢さんは、茨城県の名門・鹿島学園で選手としてプレーした後、指導者を志して北陸大学へ進学。大学卒業後すぐに福山シティFCの監督として指導者キャリアをスタートさせ、Jリーグ・ガイナーレ鳥取の強化責任者やヘッドコーチとしても経験を積みました。
現在は再び福山シティFCの指揮官を務めながら、チームのJ参入、そして自身のヨーロッパ挑戦に向けて奮闘しています。そんな小谷野さんに、若くして指導者を志した理由と将来の展望、日本サッカー界における指導者ライセンス制度についてもお聞きしました。
サッカータウン・鹿島で生まれ育った幼少期〜指導者を目指すきっかけ
ーまずは現在の役職について教えていただけますか?
現在は、J1から数えてJ5相当となる中国リーグ1部の福山シティFCというチームで、監督とトップチームダイレクター(強化責任者)を兼任しています。チーム編成や選手の評価、スタッフの管理など幅広く担当しながら、2026シーズンのJFL昇格を目指して活動しています。
ー強化担当というと、選手獲得など華やかな面に注目が集まりがちですが、実際には評価面談をしたりなど、かなりシビアな側面もあるのではないですか?
そうですね。以前にJリーグ・ガイナーレ鳥取で強化部長を務めていたこともあるので、その経験を活かしながら現在の仕事にも取り組んでいます。
地域リーグには仕事をしながらプレーしている選手も多く、評価の対象はサッカーのパフォーマンスだけではありません。勤務先での働きぶりや、ホームタウン活動など、プロよりも広い視野での評価が求められます。
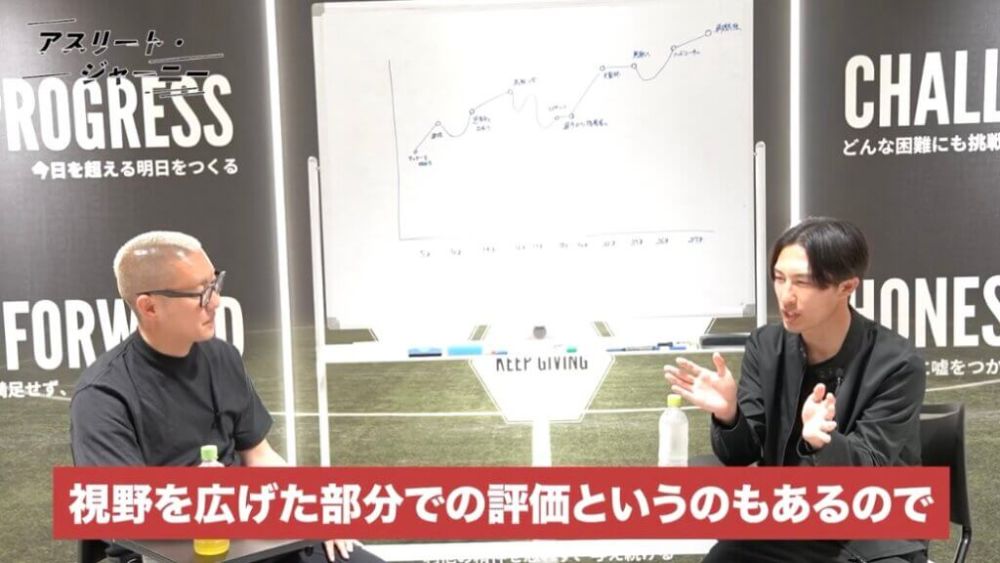
ーまるで一般企業の人事評価のようですね。現在は27歳で監督を務めていらっしゃいますが、まずはサッカーとの出会いについてお聞きしてもよろしいですか?
茨城県潮来市という鹿嶋市の隣町の出身で、家族みんなが生粋の鹿島アントラーズファンの家庭で育ちました。2歳上の兄の影響もあって、物心ついた時にはサッカーを始めていましたね。僕だけでなくその町の少年たちは、みんな鹿島アントラーズでプレーをするのが目標で、とにかくサッカーに熱中していました。
ーすごく特徴的な町ですよね。小さな自治体にJリーグを代表する強豪チームがあるというのは、特別なことだと思います。
サッカーをやっていない子どもたちも、普通にアントラーズの試合を観に行くんですよ。存在を知っていて当然という感じで、まさに“サッカータウン”ですね。
ーグラフには「10歳で選抜に入る」とありますが、順調にステップアップしていったのでしょうか?
最初にプレーしたのは、通っていた小学校の少年団です。関東の少年サッカー界では『フジパンCUP』が登竜門のような大会で、僕もサッカーを始めてからそこを目標にしていました。ちょうど10歳くらいでトレセン(選抜)に選ばれるようになったのですが、行けば行くほど、今Jリーグや日本代表で活躍しているような選手たちと競い合うことになりました。
「これが才能の差か…」と、努力ではどうにもならない部分があると感じ始めたのが、ちょうどその頃ですね。口では「プロサッカー選手になりたい」と言っていましたが、心のどこかで「現実的には難しいかもしれない」と認識しはじめた時期でした。

ー当時一緒にプレーしていた中で、現在プロで活躍している選手というと?
選抜で一緒だった町田浩樹(ユニオン・サン=ジロワーズ/ベルギー)は、身長も高くて左利きと、当時からポテンシャルがずば抜けていましたね。
同い年では三笘薫選手(ブライトン/イングランド)もいますし、高校では1学年下に上田綺世(フェイエノールト/オランダ)がいました。あとは黒川淳史選手(スパルタク・ヴァルナ/ブルガリア)、平戸太貴選手(京都サンガF.C.)など、そうそうたるメンバーが集まっていました。
ーそれでもサッカーは続けて、中学では中体連を選んだのですね。
隣町にある神栖第二中学校という、当時県内で最も強いとされていた中体連のチームに進むことを決めました。2学年上には石川大地選手(ジェフユナイテッド市原・千葉)がいて、全国大会にも出ていた強豪校だったんです。
ーちなみに、石川大地選手はやっぱり当時から凄かったですか?
もう“化け物”と言っていいくらい、圧倒的でした。技術はもちろん、カリスマ性がすごかったですね。「この人に任せておけば大丈夫」って思わせるだけの存在感があって、クールなタイプなんですけど、プレーはずば抜けて上手かったです。
ーそこで恩師と出会うとのことですが、こちらについて詳しく聞かせていただけますか?
サッカー部の顧問の先生なのですが、サッカーの技術だけでなく、人として大切なことをたくさん教えていただきました。当時「プロサッカー選手になるのは難しいかもしれない」と思い始めていた頃でもあった中で、その先生に出会って「自分も誰かに影響を与えられるような仕事がしたい」と思うようになったんです。
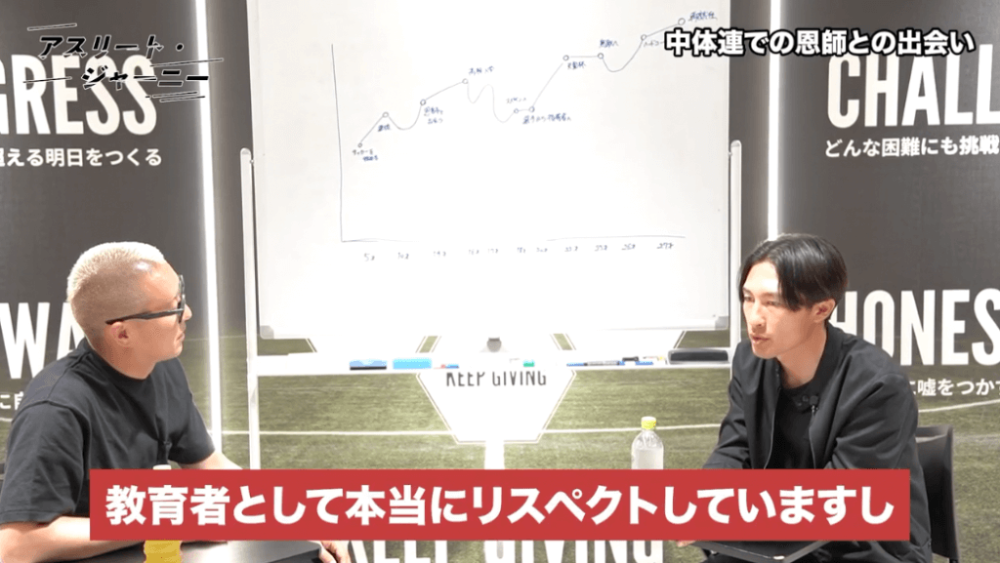
ーちなみに、中学校3年間の競技成績はどうだったのでしょうか?
1年生の時に石川大地選手の代が中心となって全国大会に出場しました。1年生の時から県選抜にも選ばれて、そこから3年間ずっと活動していましたね。
自分が3年生の時も再び全国大会に出場することができて、ベスト16まで進みました。茨城県のU-15リーグでも優勝して、県内の中体連としては唯一、高円宮杯にも出場するなど、3年間を通して充実した時間を過ごせたと思います。
当時は、水戸ホーリーホックジュニアユースやFC古河ジュニアユースなどの強豪がひしめいていた中で、県優勝できたのですごく自信になりました。
ー指導者になってみて振り返ると、「あの頃の自分でもプロになるチャンスはあったな」と感じたりしませんか?
それはめちゃくちゃ思いますね。現実じみた子どもだったというか、バカになりきれなかったというか……実際、小学生の時に選抜に入っていなくてもプロで活躍している選手は山ほどいますし、諦めるのがちょっと早かったなって、今は思いますね。
ー先ほど上田綺世選手の名前も出てきましたが、高校は鹿島学園に進学されたのですよね。
いくつか県内の高校で練習参加をしたのですが、鹿島学園が群を抜いて強かったんです。選手権の県予選を3連覇していたこともあって、「ここでやってみたい」と素直に思いました。
ただ、この高校3年間が本当にしんどかったです。信じられないくらい走るし、上下関係も厳しくて。同級生や先輩もサッカーを辞める人が多かったですし、自分も何度も辞めようか悩みました。
でも、やっぱり「ここで辞めたら絶対後悔する」「選手権に出たい」という気持ちがあって、毎日のように葛藤していましたね。
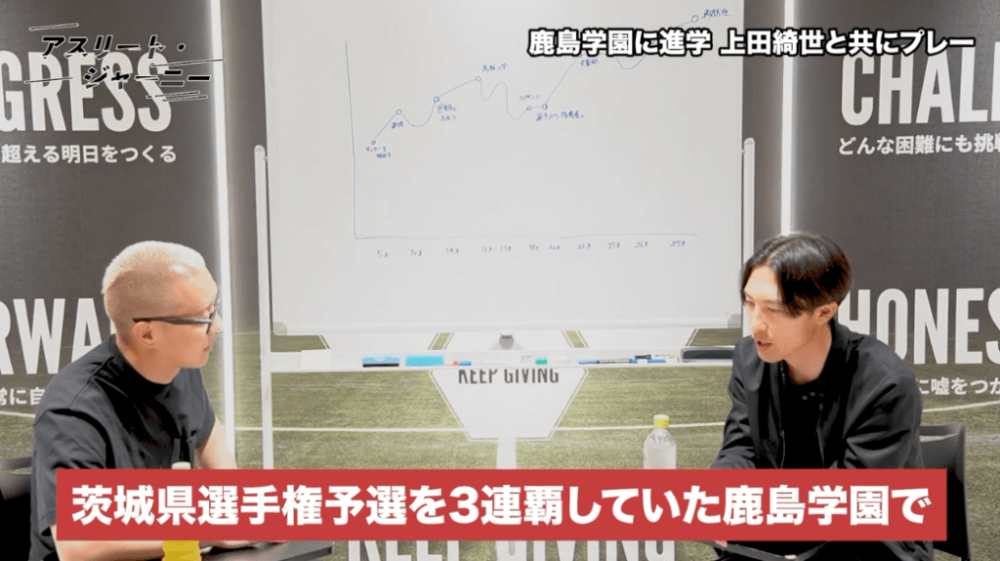
ーそんな中、グラフが上昇しているタイミングでは何があったのでしょうか?
チーム内でもカテゴリーが6〜7つくらいに分かれているのですが、自分は1年生からBチームでプレーさせてもらっていて、2年生ではAチームに上がることができました。そこからインターハイに出場するなど、少しずつ結果が出てきたタイミングですね。
しかし、高2の夏ではBチームに落ちてしまいました。監督の交代などもあり、チーム全体が少し揺れていた時期だったので、僕自身もそうですし、仲間たちも迷いながらサッカーをしていたような感覚でした。
その後、春先には再びAチームに戻ることができたのですが、試合には出場できたりできなかったりという状況が続いていて、「このままで大丈夫かな…」と不安を感じていました。ちなみに、1学年下だった綺世とは、この時にトップチームで一緒にプレーしていました。
ー上田選手は最初からトップカテゴリーでプレーしていたのでしょうか?
いえ、最初はEチームやDチームくらいだったと思います。そこから1年生の夏にはCチームまで昇格していたんじゃないかなと。
ー今では日本代表でも活躍していますが、その姿は当時から想像できましたか?
正直、まったく想像していませんでしたね。もちろん茨城県の中では素晴らしい才能を発揮していましたが、プロになるというのは誰も口にはしていなかったです。
ここで大きな学びになったのは、「どんな指導者も、選手の可能性を測ることはできないんだな」ということ。彼も最初から日の丸を背負うような道を歩んでいたわけではないですし、逆に今すごく高いレベルにいる選手でも、将来どうなるかは誰にも分かりません。
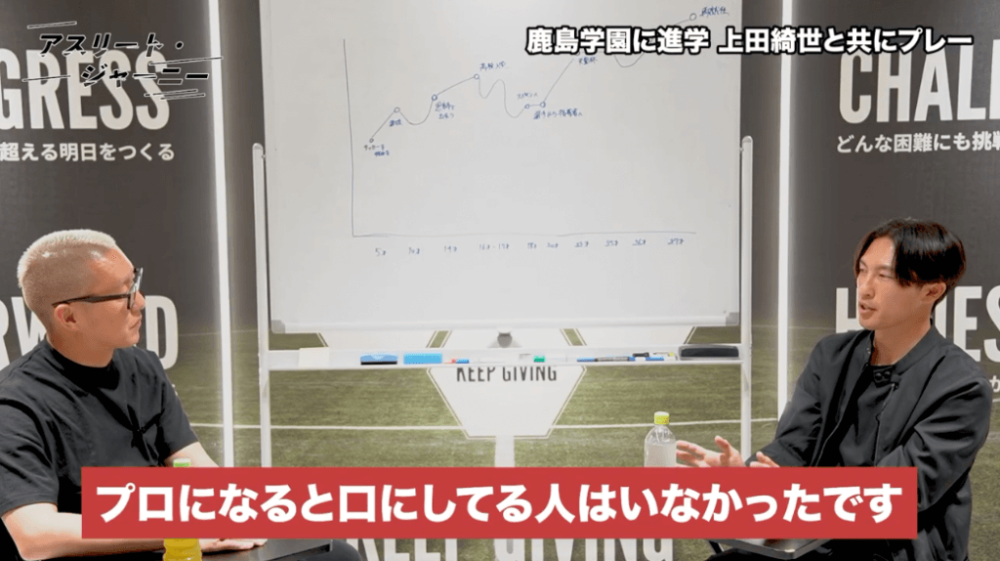
指導者としての土台となった北陸大学での経験
ーこのスペイン遠征とは、毎年鹿島学園が実施しているものですか?
そうですね。高3になるタイミングでスペインに行って、ビジャレアルのユースと試合をしたり、バルセロナの試合を観戦したりしました。
ちょうどその時期は「自分ってサッカーが好きなのかな?」と悩んでいた時期でもあったのですが、現地でメッシやシャビ、イニエスタ、ブスケツといった黄金世代のバルサの試合を見た瞬間に、「あ、やっぱりサッカーが好きなんだ」と確信したんです。
「こんなふうにサッカーを純粋に楽しめる環境を日本でも作りたい」と強く思い、それまで「人に影響を与える仕事に就きたい」とぼんやり考えていた目標が、“サッカー指導者”というはっきりとした形で見えてきたんです。スペイン遠征が、間違いなく人生の大きな転機になりました。
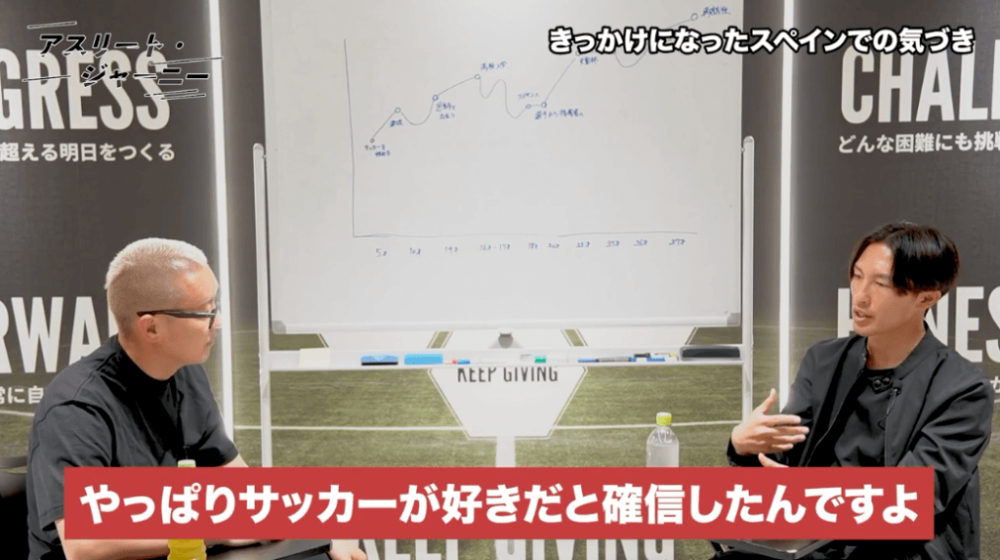
ー高校を卒業してからは、すぐに指導者の道へ進んだのでしょうか?
高3の時点で引退を決めて、「指導者としての勉強ができて、なおかつ学生コーチとしての経験も積める環境」を軸に大学を探し始めました。
関東の大学を中心に探していた中で、「石川県の北陸大学にサッカー指導者コースがあるらしい」という情報を得たんです。ちょうど、鹿島学園の監督が北陸大サッカー部の監督と知り合いで、練習に参加させてもらうことになりました。
まずは選手として練習参加をさせていただいたのですが、そこで「すみません、学生コーチを希望してるのですが、やらせてもらえませんか?」と直談判したんです。すると総監督の越田剛史先生が、「いや、お前はまだ選手としてやれる」と言ってくださって。
自分としても、将来指導者になるにあたって大学サッカーの経験はプラスになると思ったので、結果的に大学でも選手を続けることにしました。
ー北陸大という選択肢も面白いなと思ったのですが、当時は学生コーチという言葉もあまり聞かなかったですよね?
そうなんです。検索してもほとんど情報が出てこなかったですし、そもそも学生コーチ自体の母数が少なかったですよね。そんな中で、北陸大には「指導者育成をしていこう」という姿勢があり、学生コーチの受け入れにも寛容な珍しい環境だったと思います。
ーそういった環境であれば、入部してすぐに学生コーチに転身することもできたのではないかと思うのですが。
高校までは厳しい環境でやらされている感があった中で、大学では自由にプレーができて、純粋にサッカーの楽しさを味わえたというか……サッカーを「楽しい」と感じられる時間を取り戻すことができたんです。
一方で、地域の子どもたちにサッカーを教える機会もあったので、選手として感じたことを指導者として伝えるというサイクルを回すことができていた時期でした。
ー大学サッカーの経験が指導者としての土台にもなっているのですね。
現在ジェフユナイテッド市原・千葉で10番をつけている横山暁之選手も1学年上にいて、そういったプロを目指す選手が身近にいたのも良い経験になったと思います。
実は、横山選手は大学4年生の時に膝の怪我でプロの練習参加に行けず、1年間大学に残ってサッカー浪人をしていたんです。ときどき一緒に映像を見ながらサッカーの勉強もしていたので、分析の面白さを教えてくれた存在でもあります。そんな苦しい時期を見ていたので、報われて良かったなと思いますね。
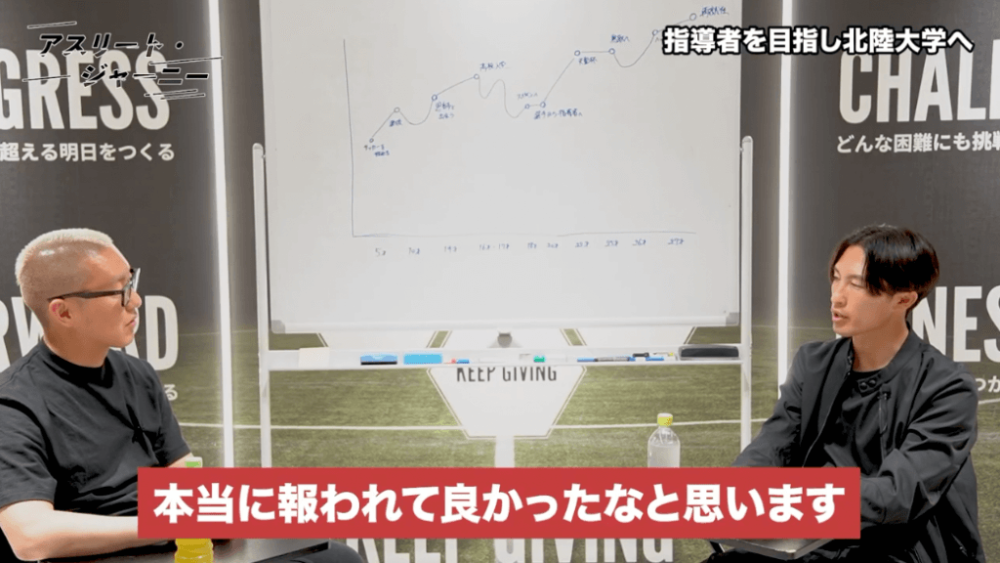
ーただ、3年間も選手としてプレーしていたら、最終学年まで続けたい気持ちもあったのでは?
僕が入学したタイミングで北陸大は北信越リーグを3連覇していて、当時は「北信越で一番強いチーム」と言われていたんです。でも、その後は新潟医療福祉大学がどんどん台頭してきて、僕と同い年の矢村健選手(アルビレックス新潟)がプロになるなど、リーグのレベルも一気に上がりました。
その中で、北陸大学は僕が入学してから全国大会に一度も出場できていなかった。それに対してチームに所属する人間として「情けないな」と感じるようになったんです。
そこで3年生の夏に選手を引退して、指導者一本で活動すると決めました。その方がチームを勝たせられるし、自分自身の将来にも繋がると考えたんです。
ー指導者に転身してからはグラフも上昇していますが、北陸大での指導者生活はいかがでしたか?
トップチームではヘッドコーチという立場で、対戦相手の分析やセットプレーの準備など練習の一部を任せていただきました。とにかく勉強するしかないと思っていたので、試合映像を見たり、本を読んだりして知識を増やしながら、小学生から高校生を指導する場を持つようにもしていましたね。

あとはチームマネジメントにも取り組みました。当時あってないようなものだった寮のルールを整えるなど、規律ある組織にするために考えたことが、実を結んだ部分もあるのかなとは思っています。
結果として天皇杯本戦に出場して、2回戦で鹿島アントラーズと戦うことができ、冬には目標としていたインカレにも出場することができました。
ーそれまで一緒にプレーしていた同世代や年上の選手に対して指導をするのは、立場的に難しくなかったですか?
最初は難しかったですし、慣れるまでには時間がかかりました。ただ、北陸大学は良い人が多くて、変なバッシングや態度が変わる選手がいなかったので、すごくやりやすかったですね。
ーちなみに当時の北陸大学はどういったサッカーを志向していたのですか?
西川周吾監督の元、4−3−3でポゼッション志向のサッカーをしていました。ペップ・グアルディオラ監督が率いるバルセロナが全盛期の時代だったので、僕自身もボールを保持するスタイルでプレーや指導する機会が多かったです。
新卒で福山シティFC監督に就任「クラブのビジョンに魅力を感じた」
ー北陸大を卒業後に福山シティFCの監督に就任されますが、どういった経緯だったのでしょうか?
もともとはJクラブの分析官になりたいと思っていたんです。当時は、筑波大学の大学院からJクラブで働く人が多かったので、そこへ進学することも考えました。
ただ、少しずつそれ以外の選択肢もあるのではないかと思うようになり、まずは自分の名前を関係者に知ってもらう必要があるなと。そこで、Twitterやnoteでの発信に力を入れることにしたんです。それがきっかけで福山シティFCの岡本佳大代表とお話する機会があり、監督就任のオファーをいただいたという流れです。
ー具体的にはどのようなコンテンツを発信していたのですか?
サッカー界での暴言や体罰などへの問題提起と、海外クラブの試合分析などの記事を書いていました。ちなみに、ポジショナルプレーについて自分なりの解釈をまとめた記事が、一番バズりましたね。
ー発信をしていると批判的な声が届くこともあったのではないですか?
そういった声もありましたが、特に気にしなかったです。選手を引退したことが大きくて、人の目を気にしている場合じゃないなと(笑)とにかく自分がスペインに行って感じた「指導者になる」という決意が固かったです。
ー当時、福山シティFCは県リーグ2部ということで、もう少し待てばもっと上のカテゴリーから声が掛かりそうな気もしますが。
正直、僕自身も「さすがに県2部は厳しいだろうな」と思っていました。ただ、岡本代表からクラブのビジョンやJリーグまでの道のりを聞いたときに、すごく魅力を感じたんです。
自分としても、日本サッカーを少しでも変えたいという思いがあった中で、過去に20代でJクラブの監督をしていた人はいなかったなと。そこに自分が挑戦することは意義があるんじゃないかと、思い切って決断しました。
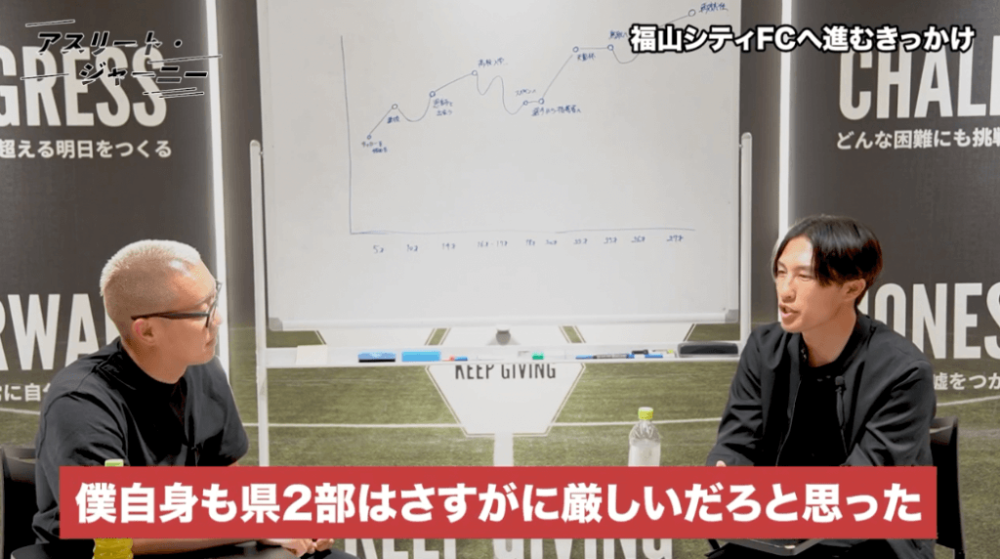
ー当時のカテゴリーも含め、クラブを取り巻く環境はいかがでしたか?
練習はゴールも無い河川敷で行うこともありましたし、始動直前なのに備品が揃っていないようなところからのスタートでした。自分で必要な備品を注文したり、練習中にボトルを置く位置を変えたり、マネージャーのような仕事もやらざるを得なかったです。というのも、当時専属のスタッフとして働いていたのが僕だけだったので、やるしかないという感じでした。
ーそんな環境からスタートして、いきなり天皇杯出場という成果を残しましたね。
天皇杯への思いが強かったのには理由があります。そのシーズンは、コロナ禍で思うように売上が伸びず、クラブがクラウドファンディングを実施していました。
当時のチームは、地域リーグ昇格の可能性が消滅してしまい、何も結果を残せていなかったのにも関わらず、目標の500万円を大きく超える約800万円もの支援が集まったんです。
そこから僕だけではなくチーム全員が「応援して支えてくれる人たちのために戦おう」と、すごく一致団結するようになりました。その思いでなんとか勝ち進み、準々決勝でブラウブリッツ秋田さんに負けてしまったのですが、ベスト6を達成(※)することができました。
※天皇杯での成績:広島県代表として第100回大会に出場。県リーグ1部所属ながら準々決勝進出を果たし、大学・社会人・Jリーグ全国約2,400チーム中ベスト6を達成。
世界で活躍する指導者を生み出すために必要なライセンス制度の在り方
ー天皇杯での躍進などで福山シティFCの知名度も上がったなかで、ガイナーレ鳥取の強化部長に就任されます。こちらはどのような経緯があったのでしょうか?
一番は、指導者ライセンスを取りたかった、ということですね。福山でそのシーズンで昇格できる可能性が無くなってしまったときに、Jクラブに移ってライセンスを取りにいくという決断をしました。
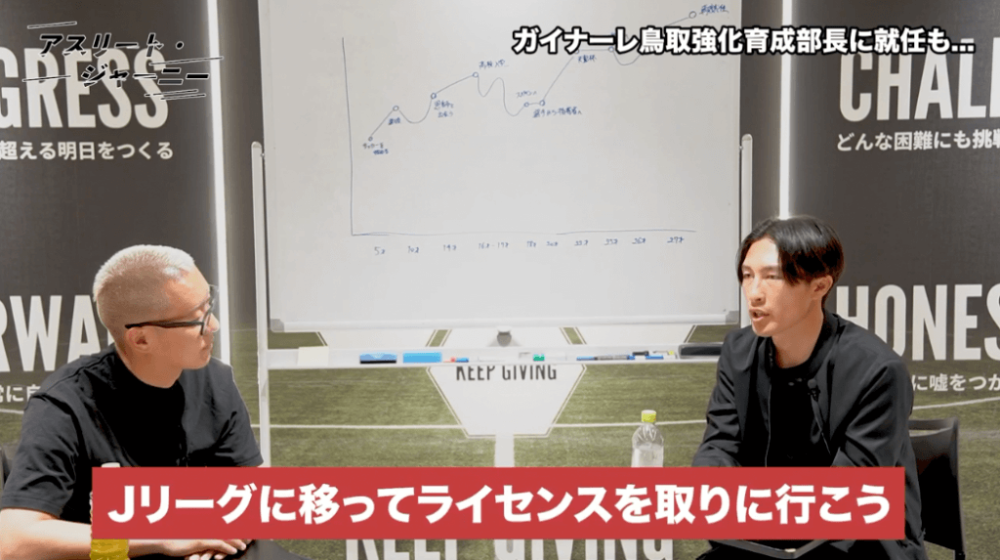
ー就任直後はグラフが下降していますが、何があったのでしょうか?
就任したタイミングが年末年始の膨大な契約書をまとめる時期だったんです。クラブや選手のことを把握できていない状態で、口頭合意された内容と契約書の数字などが間違っていないかをチェックするんです。契約書の作り方も分からなかったので、もうパニックでしたね(笑)
ーその後は、ヘッドコーチに就任されました。
強化部の仕事に慣れてきた矢先に、監督が交代することになったんです。ちょうどJ3からJFLへの降格制度ができたシーズンだったので、クラブのために自分の力を使って、どうにか残留させるしかない状況でした。自分の頭の中がごちゃごちゃになっているとかは、もう関係なかったです。就任時は18位だったチームですが、最終的には6位で残留させることができました。
ー翌2024シーズンもヘッドコーチとして1年間指導にあたった形ですが、どのように振り返りますか?
指導者としてJリーグで戦っていくために必要なことを学んだ期間でしたね。今J2で飛躍しているRB大宮アルディージャやFC今治といったチームがどんなレベルなのか、実際に対戦して感じることができました。
ーそのまま鳥取にいれば、Jクラブでのキャリアを積み重ねることもできたのかなと思います。そんな中で、再び福山シティFCに戻った理由は何だったのでしょうか?
まずお伝えしておきたいのは、ガイナーレがすごく良いクラブだったということです。フロントスタッフの方も含めて良い人たちばかりで、とても働きやすい環境でした。
その反面、個人的なキャリアを考えたとき、クラブ推薦の指導者ライセンスの審査に落ちてしまったことが結構ショックだったんです。
ー指導者ライセンスに推薦や審査があるのですか?
Jリーグの各クラブは、A級ライセンス取得希望者をリーグへ推薦する枠を持っているんです。僕もガイナーレに推薦していただいたのですが、書類審査で落ちてしまって……プレーや指導の経験などが考慮されるのですが、このままコーチという立場でキャリアを積んでいても、すぐにライセンスは取らせてもらえないなと思ったんです。ならばもう一回、監督として結果を出す方が早いなと思い、福山シティFCに戻る決断をしました。
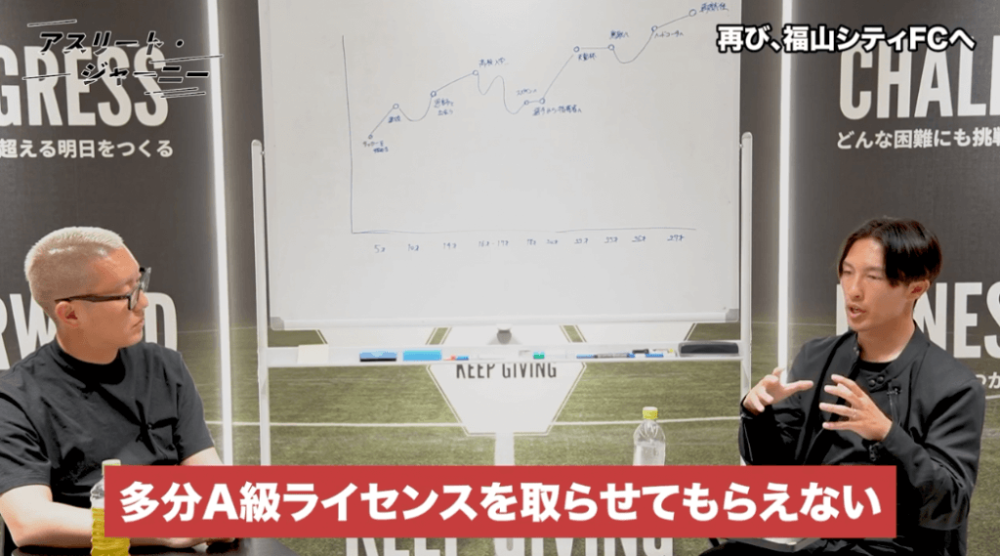
ー国内の指導者ライセンス制度には、様々な意見がありますよね。実際、A級ライセンスでJ3の監督を務められるようにする動きなども報道されています。
僕としては、ライセンス制度が指導者の機会損失や競争力の衰退に繋がるのは良くないと感じています。年齢関係なく実力のある指導者が、ライセンス制度によってチャレンジの機会を失ってしまうのは、サッカー界にとっての損失だと思いますね。
例えば、20代でJクラブの監督として結果を残すことができれば、30代からヨーロッパなど海外でもチャレンジすることができますよね。そういった意味でも、指導者が世界的に上を目指すためには、ライセンスに柔軟性をもたせることは重要かなと思っています。
ー福山で結果を残してステップアップしたいという思いも強いのかなと感じるのですが、今後についてはどのように考えていらっしゃいますか?
まずは、福山シティFCでJリーグを目指す。これが直近のビジョンです。来シーズンにJFL、2年後にはJ3という道も見えているので、自分が監督として達成できたら一番幸せに思います。

今はたくさんの選手が海外で活躍していますが、僕も将来的にはJ1クラブの監督としてタイトルを取って、ヨーロッパに挑戦の場を移したいと思っています。なるべく若いうちにライセンス取得をして、30代後半ぐらいで実現できたら理想ですね。
またこうした自分の挑戦から議論も生まれてくる思うので、日本サッカーの風向きが少しでも良い方向に変わるように、毎日を過ごしていきたいと思っています。
ーこれまで関わってきた選手たちと同じチームで戦いたい、などの思いはありますか?
同じチームで、とはあまり思いません。ただ、例えば綺世が活躍しているのを見ると、僕も嬉しいですし、負けていられないなという気持ちになります。彼らに負けないように、日本サッカーのために戦っていきたいという思いは持っています。
動画はこちら
<前編>
<後編>