愛媛オレンジバイキングス副社長・中根弓佳氏が語る、サイボウズ流「クラブ経営戦略」の全貌

スポーツチームの職員や企業でスポーツ関連の業務に携わっている方などを対象に、その職へ就くまでの経緯や仕事に対する思い、そして学生時代に取り組んでいて役に立った経験などを伺い、スポーツ業界を目指す方へ有益な情報を発信していく企画『スポーツ業界の本音とリアル』。
今回は、サイボウズ株式会社 執行役員 人事本部長であり、株式会社エヒメスポーツエンターテイメント(愛媛オレンジバイキングス)の取締役副社長も務める中根弓佳さんにインタビュー。
サイボウズがスポーツチームの経営に参画した理由、Bリーグ理事として感じた「悪しき体育会文化」への問題意識、サイボウズ流DXで挑む「勝てるチームと稼げる組織」の両立、そしてバスケとアリーナを核にした地方創生について伺いました。
サイボウズが目指す「チームワークにあふれる社会づくり」
ー中根さんの現在の役職と、愛媛オレンジバイキングスでの役割について教えてください。
サイボウズでは人事本部の責任者として、会社のチームワークを良くする人・組織づくりを担当しています。愛媛オレンジバイキングス(以下、バイキングス)では取締役副社長として、組織とチームを改善し、勝利を通じて街づくりに貢献する役割を担っています。
ーIT企業であるサイボウズが、クラブの経営に参画したのはどういった経緯なのでしょうか。
まず、バイキングスの経営は非常に苦しい状況でした。さらに言うと、財務と戦績の両面で厳しく、会社を一緒に経営してくれるパートナーを探しているというバイキングス側の事情がありました。

一方でサイボウズは、IT製品でチームのDXを支援していますが、街や業界全体で使っていただくことで、チームワークにあふれる社会づくりが加速されるだろうという戦略を以前から持っていました。
そんな折、サイボウズ社長の青野慶久にバイキングスからお話をいただき、「これだ」と直感しました。スポーツチームは地域に根ざした存在で、そこに私たちが経営に参画することで、街全体を一つのチームにし、それによって我々が得意なDXでご支援できる。まさに私たちが目指していた形が作れるのではないかと考えました。すぐにサイボウズ内に「チームワークあふれるまちづくり室」というのも作りました。私は同室の室長も務めていますが、そのまちづくり室の取り組みの一環として、スポーツを活用して街づくりをやっていこう、という経緯です。
ー「チームワークあふれるまちづくり室」とクラブの経営参画は、順番はどちらが先なんですか?
同時です。ただ、この点には難しさがありました。私はBリーグの理事として、チームを核に街が盛り上がる事例をいくつも見てきました。地方創生につながる手応えはありますが、一般の方には試合やファンクラブといった“見える部分”しか伝わりません。実際には、地域の経営者のネットワークや自治体との連携といった“水面下”の動きが大きいのです。サイボウズはその水面下と見える部分の両方にアプローチしますが、社内でその価値を理解し、共感して投資に踏み切ってもらうまでのプロセスは正直、苦労しました。
Bリーグ理事就任と「悪しき体育会文化」への問題意識
ーちなみにBリーグの理事にはどういった経緯で就任されたのでしょうか。
Bリーグが成長期に入るタイミングで、組織づくりの経験があったことから理事のお声がけをいただきました。
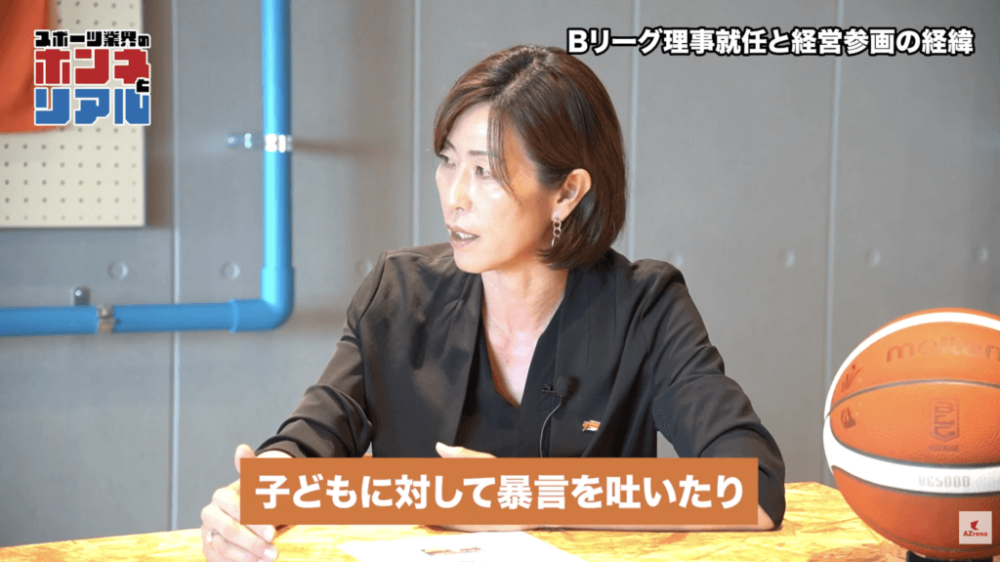
ただ、引き受けた背景には個人的な問題意識も強くありました。娘がミニバスをしており、遠征先で監督やコーチが子どもに暴言を吐いたり椅子を蹴ったりする場面を目にして、強い違和感を覚えました。いわゆる「悪しき体育会文化」ですね。こうした文化が小中高の段階で固定化されると、やがて企業にも持ち込まれかねない。サイボウズで組織づくりに携わってきた立場から、強い危機感を抱きました。もちろん無くすべき文化ですが、「変わりましょう」と呼びかけるだけでは現実は動きません。
一方で、プロスポーツの現場では外部のビジネス視点が入り、改善が進んでいると感じていました。トップが良いカルチャーを示せば、その影響は下の世代にも波及します。そこに変革のヒントがあると考えました。ちょうどサイボウズも組織拡大の只中にあり、Bリーグも成長期でしたので、自分の経験で貢献できると判断し、理事をお引き受けしました。
ー愛媛での手応えについてはいかがでしょうか?
松山という都市や道後温泉があり、南へ行けばアドベンチャー感のある地域もある。本当に豊かな県だと感じています。
一方で、愛媛は人口流出が非常に激しく、特に女性と若者の流出が課題です。バスケットは室内競技で天候に左右されず、日焼けもしません。小さなお子さんも連れて来やすい。20代後半から30代のお母さんも発散の場所が欲しいと思いますし、お子さんを置いていけない場合でも、一緒に来場できます。地域に“好き”を積み上げるコンテンツになれると考えています。
最初はよそ者として警戒されるのではと心配もしましたが、実際は歓迎してくださる方が多いです。もし懐疑的な方がいらっしゃるなら、最後は信頼を積み重ねるだけだと思っています。
kintone導入で進める、フロント業務の「脱・属人化」
ースポーツ業界の労働環境について伺います。特殊な面も多いと思いますが、DXで改善できる部分は大きいのでしょうか。
ここに関しては大きな伸び代があると考えています。やはり最大の課題は、エンタメ特有の「時間のズレ」、つまり土日や夜間に業務が集中することです。これが、育児や介護中の方々の参入障壁になっています。 解決策は、DXによる業務効率化に加えてワークシェアリングを導入することです。時間に制約のある方とない方が、互いの空きを補い合える仕組みを作ることが大切だと考えています。
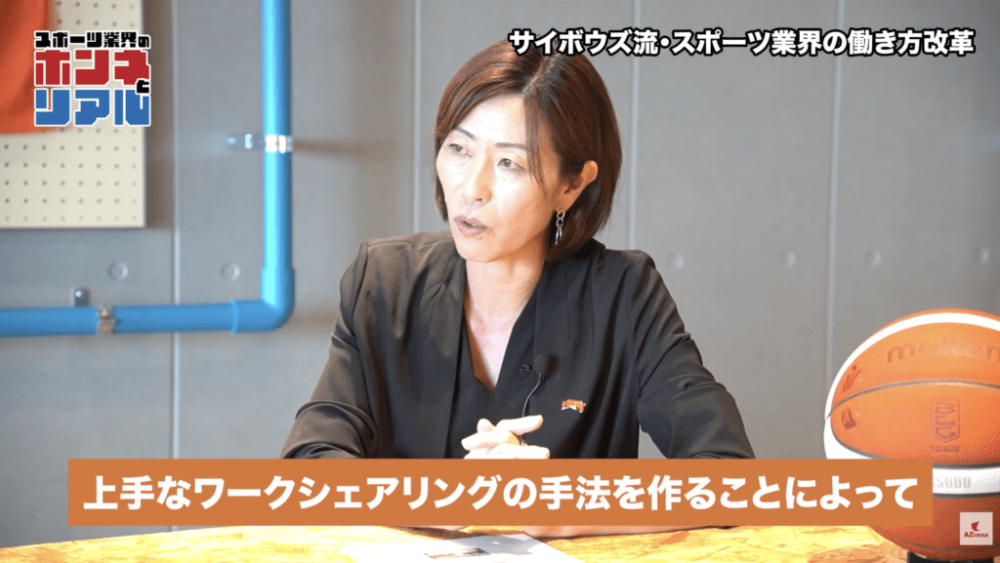
そしてその実現には、DXを活用した情報共有の徹底と属人化の解消が欠かせません。個人の頑張りに頼る「個人戦」から、プロセスで回る「チーム戦」へ移行することが、業界の持続可能性を高めると考えています。
ーサイボウズ社内でも、そうした働き方の環境づくりを進めてきたんですか?
はい。サイボウズがまさにそうでした。過去に離職率が非常に高い時期があり、採用にも苦労しました。そこで時間や場所の柔軟化を進め、フルタイム以外の人も前提に組み立てる発想に切り替えました。たとえば「60%なら働けます」という人と「40%なら働けます」という人を組み合わせ、チームとして100%の力を発揮できるようにする。東京にいない人も、工夫次第で戦力として巻き込めるようにしてきました。そのうえで、情報共有を徹底し、公明正大に物事を進め、対話と議論を大切にする。多様な個性を尊重しながらチームをつくる。こうした取り組みは一定の成果が出ていると感じています。業界やITリテラシーの違いはありますが、考え方そのものはスポーツの現場にも応用できるはずです。
ー成績と収益の両立は難しいと思いますが、クラブとしてはどうお考えでしょうか。
両立の難しさは確かにあります。実際、成績と投資は完全に比例はしませんが相関があると考えています。だからこそ今季はトップチームへの投資を適切に増やしています。ただし、選手だけに偏らずフロントにも投資し、運営の地力を高めないと、今年良くても来年につながりません。
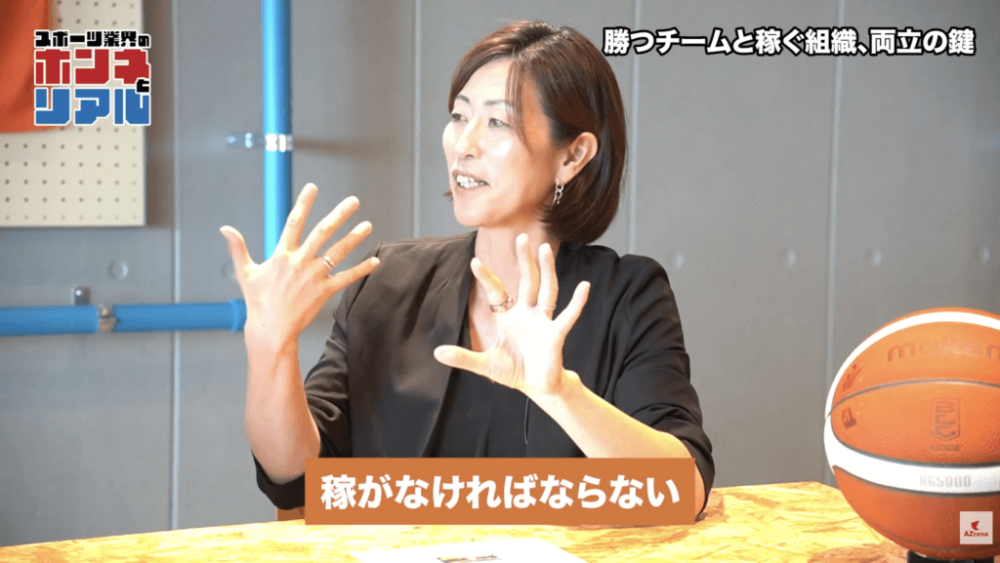
リーグは相対競争ですので、こちらだけ人件費を削れば勝てず悪循環になります。重要なのは“稼ぐ力”を高め、投資原資を自ら生み出すこと。スポンサーは大切ですが、持続的な土台はファンです。会場体験を磨いて有料比率や単価を適正化し、リピートを増やす。そこで得た収益を再びチームと運営に投資し、成績と経営の循環を回していく。その設計で両立を目指しています。
ーなるほど。今は投資フェーズということですね。
その通りです。最優先は、来場いただくお客さまを体験価値でファンへと育てていくことです。同時に、私が特に担うのはフロントの組織づくりと業務改善で、ここはサイボウズが強みを発揮できる領域です。
ーフロントを育てて、誰が入っても回る組織をつくるイメージでしょうか?
はい。いまサイボウズの製品であるkintoneをバイキングスにも導入し、ゼロから設計しています。導入から約1か月半、どの情報をどのカテゴリーで、誰に、いつ届ければ業務がスムーズになるのかをみんなで考え、アプリをつくっている段階です。現場には曖昧な部分が多く、「これは誰が判断すれば進むのだろうか」となりがちですが、システムに落とし込むと「プロセスを進めるのは誰か」「承認ボタンは誰が押すのか」を決める必要が出てきます。そこで「今まで曖昧だったね」と気づける。やることは山ほどありますが、改善と前進の実感があります。
アリーナ建設は地域全体が「チーム」で取り組む課題
ー人を集め、地元に楽しんでもらうという点で、アリーナは鍵だと思います。進捗についてはどうですか?
まだこれからです。まずは現行の器が小さいので、「チケットが取れない状態」をつくることが今季の目標です。そのうえで、アリーナはぜひ実現したいと考えています。

ーアクセス面は現在どのような状況でしょうか。
現在は松山コミュニティセンターを使用しており、街の中心にあってアクセスは非常に良いです。ですので、まずはここで「満員で入れない」状況をつくるのが先だと考えています。
ー将来的には松山駅近く、という案もあるのでしょうか。
その案も含め、場所はまだ確定していません。バイキングス専用ではなく、複数の競技やコンサート、MICE、防災拠点としても使える公共資産としてのアリーナを想定しています。バスケットの稼働は年間およそ30日程度ですから、設備や収容人数、立地を総合的に検討し、愛媛県の皆さまと協議している段階です。
ー行政の理解も大事ですよね。
地方創生の視点は重要ですが、規模の大きな投資ですので行政だけでは成立しません。地域全体が「チーム」となって取り組む課題だと考えています。民間主導の事例もありますし、やり方は一つではありません。私たちも学びながら、最適なスキームを模索しているところです。
愛媛県民も巻き込み、地域経済の循環を創出する
ー今後、パートナー企業はさらに増やしていく方針ですか?
まだ増やしたいですし、余地は十分にあります。伸びていない理由は、まず「弱い」という事実すら知られていないことです。「弱い」と認識され、勝てと言われる。つまり批判されるくらい認知されたいのです。認知が進めば、「応援しよう」と言ってくださるスポンサーは必ず増えます。現在も200社近くのスポンサーにご支援いただいていますが、継続価値を感じていただくために、強くて誇りに思えるチームづくりと、知っていただく取り組みを両輪で進めます。

ー将来的にBプレミアへ進むことで、相手チームのブースター来場による波及効果も期待できるのかなと。
その通りです。実際、今のB2でも実現できるはずだと考えています。私はリーグの理事も務めてきた立場として、バイキングスだけでなくリーグ全体、バスケ界全体の盛り上がりにつなげたいと思っています。相手チームのブースターの皆さんにも愛媛に来ていただき、地元の美味しいものを楽しんでいただきながら、それぞれのチームを応援していただく。勝った負けたをともに作り上げる、そんな世界観を実現したいです。
ー理事として、アウェイチームのブースターの来訪が盛り上がりや経済に与える効果は実感されていますか?
強く感じています。愛媛県の皆さまともご一緒しながら、スポーツを単独のコンテンツで終わらせず、観光や人流の創出につなげていきたいです。
ーありがとうございます。最後に、これから始まるシーズンへの想いをお聞かせください。
私は、バスケットは地域のプラットフォームだと考えています。バスケットボールという共通の場を通じて人がつながり、そこに産業が生まれ、テクノロジーを活用したイノベーションが芽吹いていく。その状態を実現することが私たちの成功です。そのためには、まず競技そのものが魅力的であることが欠かせません。単に愛されるだけでなく、誇りに思っていただける存在になること。強くて、チームワークが素晴らしく、誰からも尊敬される選手がいるチームであること。そうしたチームづくりとプラットフォームづくりを、これからのシーズンで着実に進めていきたいと考えています。